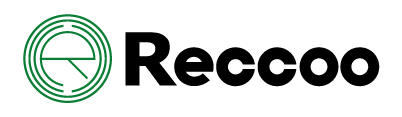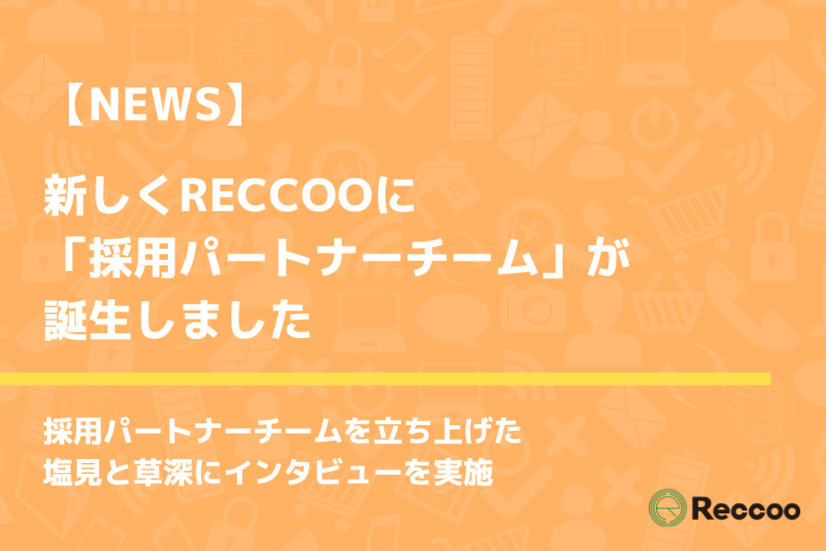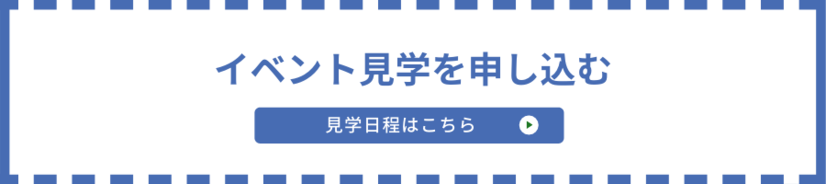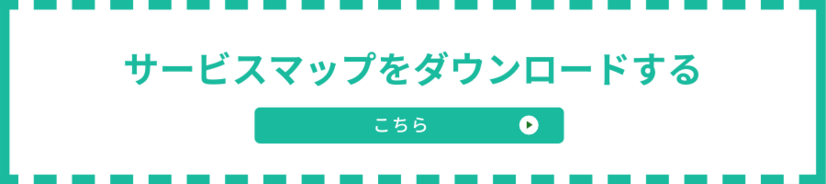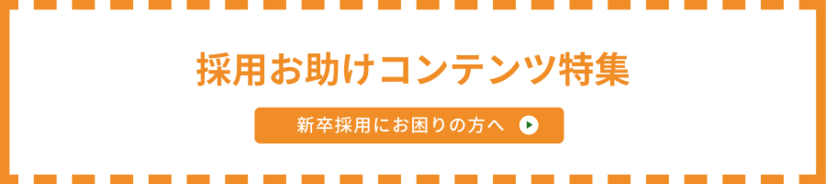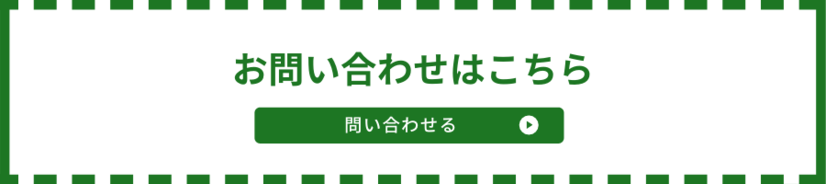新しくRECCOOに、新卒採用のための「採用パートナーチーム」が誕生しました。本記事では、新たに発足した「採用パートナーチーム」についてご紹介していきます。
目次
●新卒採用のための「採用パートナーチーム」
●なぜ「優秀な学生」だった人材が、組織で活躍できないのか
●「採用」と「経営」を近づける
●採用の上流設計から成果までの伴走
▼en-courageとは/RECCOOとは
▼おすすめ情報/資料ダウンロード
●新卒採用のための「採用パートナーチーム」
「採用パートナーチームが誕生しました」
株式会社RECCOOでは、このたび経営企画室の塩見拓也(しおみ・たくや)とCOO草深生馬(くさぶか・いくま)が
新卒採用のための「採用パートナーチーム」を立ち上げました。
RECCOOが提携する日本最大級のキャリア教育支援NPOエンカレッジ京大支部にて組織の草創期を支え、JTを経て現職に就いた塩見と、
Google人事部 Talent and Outreach Programs(学生向け採用企画室)を経て弊社にジョインした草深が、チーム立ち上げの背景について語ります。
●なぜ「優秀な学生」だった人材が、組織で活躍できないのか
ーー二人は共に30歳前後という若きチームですが、この世代だからこそ痛感している新卒採用の課題があると聞きました。
塩見:
僕も草深も、似たような問題意識をもともと抱えていて、それを共有しているうちに今回のチームが自然と発生しました。
僕自身、学生時代に、RECCOOが提携する日本最大級のキャリア教育支援NPO・エンカレッジの幹部メンバーとして、
未来の日本を担う「ハイポテンシャルな仲間」を切磋琢磨して増やしていくプロジェクトに取り組んだ経験があります。
現在、エンカレッジは全国47都道府県に約113の支部をもち、8万人(22卒、就活生全体の1/5に相当)の会員を抱えるまでに成長しましたが、誕生から7年を経てある限界を痛感するようになりました。
というのも、優秀なはずの仲間たちが、就職後、30歳前後にして「死んだ目」をしていることが少なくないからです。
学生の頃、就職した頃は、あんなに創造性にあふれていて、才気があって、非常にハイポテンシャルな人材であったはずなのに、
企業の中でそれを活かしきれず期待されていたほどには活躍できていない。
草深:
要は、学生の側のパーパス(目的)と、企業の側のパーパスが合わないままに就活でマッチングされてしまっているんですね。
企業が社会の中で何のために存在するのか、その目的と社員としてこれから入社する個人の目的が互いに認知されないまま、ズレたままキャリア選択がなされてしまっている。
塩見:
そういうもったいない現状を目にする中で、学生の側だけでなく、次は企業の側にも働きかけていく施策をしたいと、ずっと考えていました。
つまり、パーパスを一つの軸として、ハイポテンシャルな人材との「出会い方」「見極め方」「育て方」などを企業の皆様と一緒に考えていきたい、と。
草深:
それはまったく同感です。私自身もGoogle人事部 Talent and Outreach Programs(学生向け採用企画室)で長らく新卒採用マーケットを見てきた中で、学生側の施策は今すでにかなり行われていて、次は企業側の施策に取り掛かるべきタイミングではないかと個人的に感じていました。
●「採用」と「経営」を近づける
草深:
学生側にとっても、企業側にとっても、日本の採用は「唐突すぎる」と感じます。
つまり学生は、それまでほとんど実社会との接点がない中で3、4年生で唐突に就職活動をスタートさせ、何かに急かされるように何百社の情報に触れ、
実際に会いに行き、付け焼き刃の選考対策をやり、面接でそれっぽいことを話し、内定が出たらとりあえずそこに入社する。
企業の採用担当者の側は、「今年は100人新卒採用してね」という数字が、ほぼ何の脈絡もなく現場に落ちてきて、その数字を確実にデリバーすることを求められる。
しかし、そもそもどんなビジネス上の課題を会社が抱えているかを理解しなければ、最適な人材の提案、採用の設計、
人材のポテンシャルを最大化させるためのトレーニングなどに、一貫した戦略を落とし込むことができません。
しかし、こういった一連の思考を働かせる機会が、すっぽり抜け落ちてしまっている採用の現場は少なくないでしょう。
塩見:
学生にとっても、企業の採用担当者にとっても、唐突すぎるこのありかたが、冒頭に話したような「死んだ目をした、かつてのハイポテンシャルな学生たち」を生んでしまっている。
草深:
僕たち「採用パートナーチーム」の取り組みを通じて実現したいのは、第一に「経営」と「採用」を近づけることです。
Googleでは、経営と採用が密接につながっていました。
今、経営面でこういう課題を抱えているから、それを解決するためにこういう人材が必要で、だから新卒採用に対しては(経営の観点から)こういう期待値を持っている、
という会話を、僕のような採用担当者と組織のトップが頻繁に交わしていました。
現時点で、新卒採用担当の方に、「なぜ御社では、新卒を採用するのですか?」と訊けば、「自社のカルチャーをドライブするため」と答える方が多いと思います。
つまり、そこに経営の現状に対する明確な理解や、将来の展望に基づいた経営戦略が埋め込まれていない場合がほとんどです。
経営者が採用の現場を完全に理解するのは難しいでしょうし、逆に採用担当者が経営のすべてを理解するのは無理でしょう。
でも、両者をできるだけ近づけ、経営のマインドをもって採用活動を行える人事を日本企業の中に増やしていくことは、学生にとっても、企業にとってもよい結果をもたらすと信じています。
●採用の上流設計から成果まで伴走
塩見:
RECCOOはまだHR業界では設立から日の浅いベンチャーに過ぎませんが、私も草深も大手企業でのキャリアを手放して身を投じたいと思うほどの魅力がありました。
それは、RECCOOには、採用の上流設計から実際の成果まできちんと約束できるだけのアセットがあることです。
つまり、提携するエンカレッジが日々育成している優秀な学生たちと、クライアント企業様約500社と共に築き上げてきた実績が、RECCOOの貴重な財産なのです。
「採用」と「経営」を近づけた上流の設計から、採りたい学生の母集団を形成し、適切な採用プロセス設計、マーケティング戦略、
クリエイティブを含めたブランディング、そして最終的なクロージングまでワンストップで手がけられる企業は、他にないと思います。
特に提携するエンカレッジを活用して「御社が本当に求める」学生をピンポイントでご紹介できます。
これはメンター制度で1対1の面談を全国8万人(22卒想定)に行うからこそ可能なことです。
草深:
そうですね、「上流設計は任せてください」というよくあるHRコンサルティングではなく、
上流設計から、学生との接点創出を通じた成果のコミットまできっちり一気通貫でやれるのが、RECCOOの最大の魅力だと私自身感じています。
長らく人事の現場にいた人間として、私はいわゆる「HRコンサル」をあまり信用していません(笑)。
その会社のことは、その会社の人が一番よく知っているに決まっています。
もちろんコンサルティングファームの持つ独自の方法論が大きな助けになることもありますが、
本来はその会社の人間が会社内で解決まで導けることがいちばんです。
だから、私たちのチームがこれからクライアント企業の皆様とお仕事をしていく際には、その前提に立って、「壁打ち相手」として全力で伴走していきたいと思っています。
「答えは絶対に御社が持っている、それを見つけるためのお手伝いをさせてください」と。
塩見:
また、私も草深も経営メンバーとして、日々経営の厳しさを身に沁みて感んじている立場でもあります。
だからこそ、すべてのクライアント企業の皆様に対して、とことん親身に経営視点で共に考える伴奏者でありたい。
したがって、コンサルタントではなく、パートナー。
「採用と経営を近づけることで、一人ひとりのポテンシャルを最大化したい」。
その理念に共感してくださる企業の皆様と一緒にお仕事をしていきたいです。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
RECCOOの「採用パートナーチーム」は2020年10月からサービスをスタートしました。
今後ともどうぞ塩見と草深の「採用パートナーチーム」をよろしくお願いいたします。
▼キャリア教育支援NPO en-courage(エンカレッジ)とは?
日本全国100以上の大学に支部を持ち、
これまでに【10万人以上の学生】の就職活動を支援してきたキャリア教育支援NPO。
「日本の就活を変える」というビジョンに共感いただく企業様も日々増えています。
エンカレッジを活用する学生は21卒5万人、22卒約8万人と会員数を次第に伸ばし、23卒会員数は11万人見込みとなっております。
▼公式HPはこちら
キャリア教育支援NPO en-courage(エンカレッジ)
▼株式会社RECCOOとは
株式会社RECCOO は、エンカレッジと包括的業務提携を結び、上位校を中心とした学生の採用を継続的にサポートしています。月間100万PVを誇る求人媒体への情報掲載や、イベント開催やご送客を通じた接点創出、さらには学生との面談を通した個別紹介など幅広いサービスを展開しております。
これまでに500社以上の企業様とのお取引がございます。
▼公式HPはこちら
株式会社RECCOO