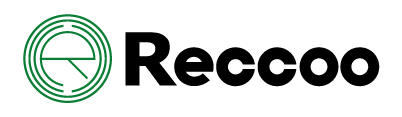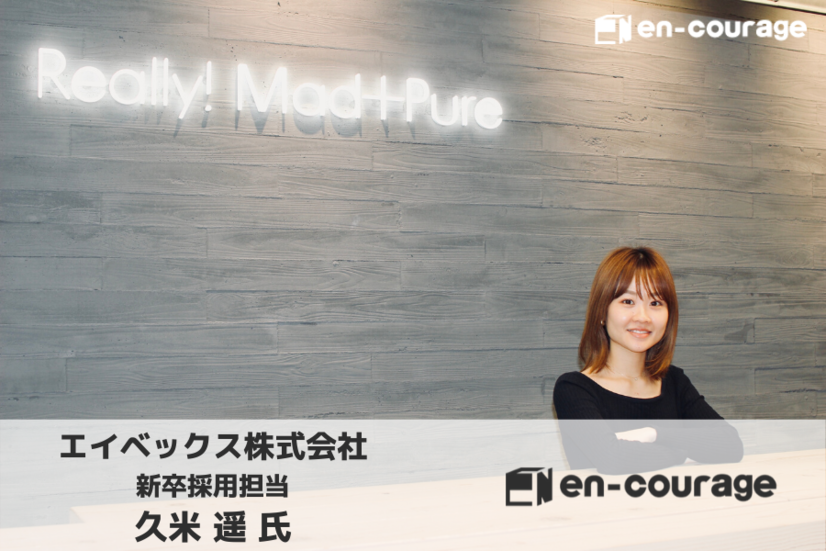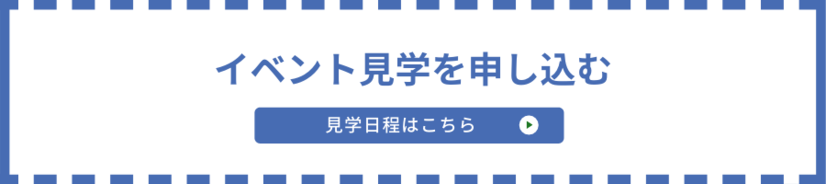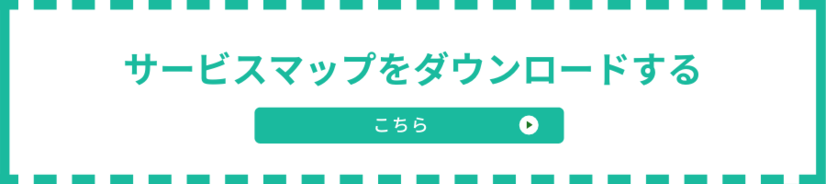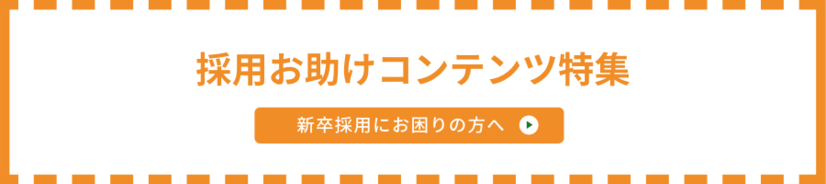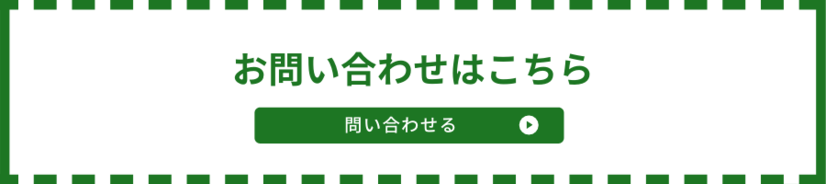新卒採用支援サービス「エンカレッジ」を利用する企業の人事担当者にインタビューする企画。第7弾は、エイベックス株式会社で7年間人事を務める久米さんに話をうかがいました。
会社のイメージを正しく伝え、求める人材に戦略的にアプローチする。
エンタメ業界の人気企業だからこそ感じる新卒採用の課題と、エンカレッジに魅力を感じる理由とは?
*株式会社RECCOOサービスマップは、ページ下部のフォームからダウンロードが可能です。
◆「エンタメ業界」の認知を超える。求める人材と出会う難しさ
ーよろしくお願いします。はじめに、久米さんご自身の自己紹介をお願いします!
久米さん:
はい、私は2013年の4月に新卒でエイベックスに入社しまして、入社から7年間ずっと人事をやっています。うちは基本一括採用なので、入社してから配属が決まるんですけれど、初期配属で人事になって最初の1,2年は、主に研修に関わっていました。具体的には、全社の研修プログラムを作ったり、後輩の新卒研修や内定者研修を企画したりしていました。
3年目くらいからインターンの立ち上げに関わり、徐々に採用領域にシフトしていき、新卒4年目くらいから採用担当になり、今に至ります。
その間で産休と育休を取って一年お休みしており、2019年の9月に復職しました。
ーでは人事としては8年目、新卒採用担当としては5年目という人事に染まったキャリアなんですね。採用チームはどういう体制なんでしょうか?。
久米さん:
研修と採用の領域で一つのチームが組まれていて、メンバーはマネージャー含め5人です。そのうちメインで採用を行っているのは2人ですね。
イベントに出るときなどはチーム内で協力しています。
ーなるほど。では早速採用のお話を聞かせてください。現在(2020年1月)は、21卒採用の真っ只中かと思います。知名度の高い企業様だと、募集がたくさん集まる傾向にあると思いますが、採用を進める中でどのような点を重視していますか?
久米さん:
うちは事業の幅も広ければ、職種も様々あるので、「こういうスキルを持っている」というよりは、社風にマッチするかという人物面 や、エンタメ業界・エイベックスという会社で働く理由が本人の中できちんと腹落ちしているか、などを重視しています。母集団を大量に集めるというよりかは、できるだけコンパクトで確度の高い母集団が集まるようなアプローチをしたい、という考えをベースに採用活動を進めています。究極的には「母集団の数=採用人数」がベストです。
ー具体的に、社内で活躍する人物像は言語化していますか?
久米さん:
人物像でいうと3つあって、「モテる人」「うごく人」「つよい人」。
「モテる人」というのはつまり「人からモテる人」。一緒に仕事をしていて気持ちがいい とか、またこの人に仕事をお願いしたい、と思われるような求心力のある人。
「うごく人」は、会社としても業界としても変化が大きい環境なので、その変化をポジティブに捉え、自分自身も変わっていくことできる人、またそのような環境の中で自ら考えて動くことができる人 を求めています。
3つめの「つよい人」は、そもそも業界のイメージ上どうしても、アーティストや作品といったキラキラした表側が見えやすいので、「何か楽しそう」「華やか」という第一印象を持つ学生さんも多いんです。でも当然のことながら実際の仕事は地道なこと、泥臭いことのほうがずっと多い。
そこがギャップになりやすいんですよね。
なので、あえて求める人物像として「つよい人」を掲げています。心身ともに強さも求められますし、ヒットを作る上では、自分が「これがいい、こうやるべきだ」と思ったことをある種頑固に、芯を持って貫き通す強さ が必要だったりもします。
つよくてうごけてモテる人、うちで活躍するなら大事な要素です。
ー業界のイメージ、確かに大きいですよね。toC方面のメーカーやエンタメ業界は初めから学生の認知があるので、それがいい面でもありつつ、実際の仕事の大変さや地道さが伝わりにくかったり。そのイメージをひっくり返すことは意識していますか?
久米さん:
そうですね。 もちろん大前提として「エンタメが好き」だとか、「エンタメを通じて世の中の人を感動させたい、喜ばせたい」という思いはすごく大事です。表に立つアーティストやエンタメコンテンツの作り手であるクリエイターに対してもリスペクトの気持ちを持てる人であって欲しいので、入り口としてエンタメに興味があって受けてくださることはすごく大歓迎なんです。
ただ、今まで自分がユーザーとして享受していた楽しさと、仕事として関わることは全く違う世界です。それを理解した上で仕事にしたいと思う方に来てもらえるように、情報の出し方を考えるようにしています。社員の仕事の様子やコメントを通じてそういったメッセージを伝えたり、本選考を受ける前の学生さんとのコミュニケーションの中で人事からそこを伝えるようにしたり。
またイメージをひっくり返すという点においては、世の中的に「芸能の会社」「音楽の会社」という認知が先行している中で、今の会社の実態を掴んでもらいにくいという課題感を持っています。それによってターゲットとなる学生さんにそもそも選択肢に入れてもらえないケースもありますし、会社や仕事への理解が浅く入社後のギャップが生まれやすくなってしまいます。
まだまだ模索中ではありますが、最初の接点でいかに会社としてのイメージを正しくアップデートしてもらえるような情報を出していくか というのがひとつと、選考の過程、「エイベックスで何がやりたいか」だけではなく学生さんの「やりきった経験」や「自分の意志を持って何かをやり切った経験」などを軸に、過去の経験やその元となる価値観 などをかなり深掘りするようにしています。大学時代だけでなく、かなり遡って話を聞くことも多いです。
先ほども申し上げたように、環境変化が大きい分、事業内容や仕事の内容は変わっていく可能性があるので、変わらない部分、つまり会社とマッチする志向性を持つ方なのかどうかという点を重視することで ミスマッチやギャップを極力防ぎたい と考えています。
◆エンカレッジのイベントで感じた、地方採用の手触り
ーありがとうございます。よりよい採用を模索する中で、19卒以降エンカレッジのイベントに参加していただいてますが、どんなところに期待を持っていたんですか?
久米さん:
数年前までは、できるだけ広く訴求し多くの母集団を集めてその中から選んでいく、というやり方をしていました。
でもインターンシップをはじめとした早期の施策をやっていく中で、早い時期に出会える学生さんの中に、初めから興味を持ってもらえてはいないないけど実は「合う」方がたくさんいそうだという気づきがあり、今までの「広く浅く」のやり方だとそういう機会を逃していたのではないか という問題意識を、18〜19卒あたりから持つようになりました。
「エンカレッジ」というワードは、なんとなく他社さんの話を聞かせてもらっている中で耳に入っていて。そんなとき、とある人事の方からご紹介いただいたのがきっかけです。
もともと、学生さんと密に接触できるパイプや、地方に効果的に訴求できるパイプをずっと探していました。実際に参加してみると、今まで使っていたサービスやイベントとは全然違う仕組みで、学生さんとの距離感が近く一人一人に対して訴求しやすい環境でした。
大学ごとに支部があったりとか、「学生が学生を育てる」組織であるという点も含めて、いいなと思っています。そういった学生組織との連携がしっかりあるからこそ、営業担当さんをはじめ、運営側の皆さんが 学生さんのリアルな動向や最新の情報 をすごく詳細に把握されているんですよね。何か知りたいことがあって質問するとだいたい解決してくれます(笑)そういった意味でも採用活動を進める上ですごく頼りになる存在ですね。
ーそうですね、早期学生との交流や、少人数や一対一のコミュニケーションの場は、エンカレッジならではかもしれません。少し率直なところを聞きたいのですが、昨年は地方を中心にエリア別イベントにいくつか出ていただきました。東京の学生と比べて違いを感じる部分はありましたか?
久米さん:
「結構違うな」って印象はあります。ありがちな表現にはなってしまうのですが、地方の学生さんはすごく純粋だし素直で伸びしろを感じる方が多いです。
変に「就活」に染まらずに、でも成長意欲があって、ポテンシャルを感じさせてくれる学生さんが多いので、純粋に一緒に働きたいなと感じる方に出会えることもよくあります。
ー就活という型にはまりすぎていないところはおそらくありますね。逆に、問題意識と課題は感じましたか?
久米さん:
そうですね。地元にも当然いい企業がたくさんあると思うので、地方の学生さんはまず「地元に残るのか?東京に出るのか?」というところから考えますよね。
ある意味関東の学生さんとスタート地点が違う中で、東京を含めたいろんな業界や企業を見てほしい、視野をもっと広げてほしいな、というのは率直に思いますね。
正直、エンタメ業界に関しては企業側がなかなか地方に行けていないというのもあると思うんですよ。うちも含めて「あんまりエンタメ企業が地方で説明会をやっていない」と学生さんからも声があって。
身近な先輩も受けていないとなると、よっぽど興味がある方以外は業界自体に触れる機会がなくて、層が広がっていってなかったんだなと思いました。
いい学生さんがいるからこそ、エイベックスとしても、エンタメ業界としても、もっとリーチをしていかないともったいないなと思います。
ーおっしゃる通りで、地方の学生ってイベント数が少なかったり、交通費や現実的なリソースの関係で企業様も積極的ではない現状はあります。そんな中で、他の人事さんの目に止まる企業さんに地方行脚していただけると、エンカレッジとしてとても嬉しいです。もちろん学生の視野を広げるという意味でもそうですし、「エイベックスさんが行ってるなら」っていうきっかけになると思っていて。
久米さん:
もしそうだとしたら、それは嬉しいです(笑)
◆立教大学支部のイベントで出会った「就部両道」の学生たち
ーもう一つイベントの話を。先ほど、何かを貫いた経験を重視するとおっしゃっていました。この間参加いただいた立教大学支部のイベントがちょうどそういうコンセプトだったなと。「部活やサークルに熱を注いで、少し遅めの就活をスタートした学生」が参加した「就部両道イベント」はどうでしたか?
久米さん:
部活やサークル、ゼミだったり何か一つのことにとことん打ち込んできた学生、というところで、うちの求める人物像的に合った学生さんが来てくれるんじゃないかと思い参加しました。
あんまりこういうセグメントって見たことなかったんですよ。学生視点を持っている支部から立ち上がった企画 だからこそかもしれないですね。どういう企業を呼ぶか、どういうコンセプトでやるかという部分も、支部の方々が後輩のことを考えて企画してくれたということで、参加してくれた学生さんもすごく熱量高く参加してくれていた印象で、そういうところも魅力的でした。
ーありがとうございます。実際に採用のところで結果には繋がっていますか?
久米さん:
このイベントに来ていた学生さんは、求める人物像と近いセグメントだったので、興味を持ってもらいやすかったのか、その後開催した自社イベントにも結構参加してくれました。
実際選考を受けてほしいなと思う学生さんもいましたね。規模としては比較的、少人数のイベントだったと思うんですけど、いい学生さんに出会える確率はとても高かったんじゃないかなと思います。
それこそサークルとかで、「チームで1つのものを作りあげる」とか「人を楽しませたり喜ばせたりすることをモチベーションに行動する」という経験をしてきた方も多くいたので。そういう学生さんは、エンタメ業界で働くことに関してイメージが湧きやすい感じもして。親和性の高い学生さんたちにピンポイントでアプローチできた のはすごくいい機会でした。
ー最後に、今後のエンカレッジに対して、さらに期待していることを教えてください。
久米さん:
エンカレの地方イベントに行くと、その地域の国立大(例えば札幌だったら北大、名古屋だったら名大など)の学生さんが層として厚いイメージがあります。
もちろん優秀な学生さんが多いのですが、もう少し地方もいろんな色のある学生さんと会えると嬉しいです。
それこそうちだと美大・芸大とかにもアプローチしているんですけど、デザイン思考を持っている学生さんがいたりとか、国立大とはまた違う側面で魅力的な学生さんがいたりするので、所属する学生層の幅が増えていくと素敵だなと思いますね。
エンカレの学生さんって、先輩からの教えがちゃんと行き渡っているのか、自分のキャリアを能動的に積極的に考えよう、描こうとする方が多くて。
ちゃんと自分に合った企業を見つけようとか、そういう気持ちが行動も含めて見える方がすごく多いんですよ。そういう考えが上位校だけじゃなくて、広く波及していくと、新たな出会いがありそうな気もしています。
ーなるほど。そういう意味でも、地方の可能性をまだ感じます。エンカレッジを使う学生は年々増えていますが色んな魅力を持った学生と企業がどうしたら出会えるのか、今後とも考え続けていきます。久米さん、ありがとうございました。
*株式会社RECCOOサービスマップは、ページ下部のフォームからダウンロードが可能です。
▼キャリア教育支援NPO en-courage(エンカレッジ)とは?
日本全国80以上の大学に支部を持ち、
これまでに【10万人以上の学生】の就職活動を支援してきたキャリア教育支援NPO。
「日本の就活を変える」というビジョンに共感いただく企業様も日々増えています。
エンカレッジを活用する学生は20卒約3万人、21卒約5万人と、会員数を次第に伸ばし、22卒会員数は8万人見込みとなっております。
▼公式HPはこちら
キャリア教育支援NPO en-courage(エンカレッジ)
▼株式会社RECCOOとは
株式会社RECCOO は、エンカレッジと包括的業務提携を結び、上位校を中心とした学生の採用を継続的にサポートしています。月間100万PVを誇る求人媒体への情報掲載や、イベント開催やご送客を通じた接点創出、さらには学生との面談を通した個別紹介など幅広いサービスを展開しております。
これまでに300社以上の企業様とのお取引がございます。
ご興味のある企業様は、下記フォームよりお問い合わせください。