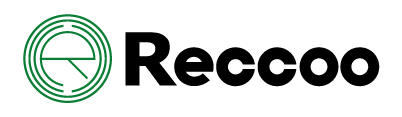就活を終えたen-courage就活生にインタビューする企画。
大学までの22年間を地元・新潟県で過ごし、東京のPR会社に就職した佐山さん(仮)。地方就活生は情報やコスト、様々な面で東京の学生に比べ不利である、と巷ではささやかれています。今回は佐山さんへのインタビューを通して地方就活生の実情に迫りました。
【企業様へ】記事末にen-courageイベントの年間スケジュール資料がございます。ダウンロードしていただき、採用活動にご活用ください。
◆悶々としていた学生時代
-今日はよろしくお願いいたします。まず初めに佐藤さんは学生時代をどのように過ごしていたのですか?
佐山さん:大学1年生はアルバイトやたまにサークルでバスケする、とかで特にこれといったことはやっていませんでした。
「このままじゃダメだな」とも思っていましたが、周りに自分が憧れるようなロールモデルもいないので、悶々としていましたね。
そんな状況が半年続いて、一念発起して留学に行きました。海外に行けば何か変わるんじゃないかと(笑)。
発展途上国で過ごして、もちろん楽しかったのですが、ただ遊ぶだけで終わってしまい、留学前に抱いていた悶々としていた気持ちは変わりませんでした。
結局、「地方」という環境のせいにしてはいけないと痛感しました。
-その後どのようなアクションを取ったのですか?
佐山:文化祭実行委員会の委員長に立候補しました。それまでは軽く活動しているだけだったのですが、自分自身を変えなきゃな、と思いました
立候補した時は周りからすごく叩かれましたが、でもなんとか説得してなんとか当選できました。
それからの1年間は組織の改革に注力しました。
◆地方ではなく「面白い人間」がいる東京へ
-ありがとうございます。続いて、就活はいつから始めましたか?
佐山:就活は3年の2月から始めました。今振り返るとすごく動き出しが遅いなと反省しています。が、当時は遅いとは思っていなかったし、むしろ地元の学生に比べれば早い方でしたね。
-佐藤さんの就活の軸と内定先を教えてください。
佐山:就活の軸は「成長企業」と「自分が一番を取れそうなところ」に行くことでした。成長に関しては売り上げと組織がどれくらい拡大しているかということを意識して見ていましたね。
結局、内定承諾した広告・PR系の会社も「成長企業」という点で、合致していました。周りの学生を見ても「勝てそうだな」と思ったんですよね。
それは学歴とかではなくて、自分の得意なクリエイティブな面においてです。そして何より、PRのことを勉強していて面白かったということも理由の1つです。
-地元・地方への就職は考えなかったのですか?
佐山:全く考えませんでした。22年間新潟で過ごしてきて思ったことがあって、地方にはとにかく面白い人間がいないな、と。
面白い人間にも色々種類があると思いますが、私は自分がその人に憧れるかどうかを「面白い」の基準にしていました。
大学2年の時に、東京で慶應大の学生と交流したことがありました。彼らは企業支援団体の学生で、「自分たちがやりたい」と行動を起こして、社会と繋がって活動しているという点で刺激的でした。
バイトやサークルなどありきたりな、用意されたものに時間を使っていた当時の自分からはめちゃくちゃ新鮮に思えたんです。
そのような自分に刺激をもたらしてくれる「面白い人」は地方にはまず、いない。東京に行かないと出会えないなと思いましたね。
◆地方では知られていない?東京の企業
-続いて、就活を通して何社と接点を持ちましたか?
佐山:説明会には50社くらいに参加しました。ほとんど東京で出会った企業ですね。地元・新潟に来てくれて、出会った企業はサイバーエージェントだけでした。
地元に来てくれたということで印象には残っていますし、選考も兼ねていたのですが周りの学生のレベルも低いので有利だなと当時は思いました。
東京の企業にはもっと地方に来て欲しいと思います。
—実際、地方にくる企業は印象に残るものですか?
佐山:もちろん残りますね。
あと東京で知名度がある企業でも地方では全く知られていない、ということが往往にして起こります。当時はサイバーエージェントですら新潟の就活生の間では知られていませんでした。
地方就活生の情報感度が低いということもありますが、事業やサービスがそのまま企業名になっていないと認知はされないんじゃないかと思います。特にベンチャー企業は知られていません。
ものすごく成長している企業でも、そもそもその成長が何かわかっていない地方就活生は多いです。魅力的な企業はたくさんありますし、地方就活生には一つでも多くの成長企業を知ってもらいたいです。
そのためにも、地方のイベントに参加する東京の企業が増えればと思っています。
◆情報格差は本当?地方就活生の実情
—続いて地方就活生に対する一般的なイメージについて検証していきたいと思います。本当のところ情報格差ってあるんですか?
佐山:いやぁ、すごいあると私は思います。当時、情報格差に気づいたのが就活を始めたての3月でした。
情報の流入経路として、友達経由とネットの検索経由の2つがあると思っています。少なくとも当時の私はそうでした。
前者の方は周りの友人の動き出しが遅かったので皆無。後者も、何かを検索するにしてもきっかけが必要ですが、そのきっかけすらなかったので、総じて得る情報は少なかったです。
-なるほど。やはり東京の学生とレベルの違いを感じることもありましたか?
佐山:それもめちゃくちゃ感じましたね。
2月に東京でロジカルシンキングセミナーというものに参加しました。旧帝国大学、早慶の学生と、フェルミ推定をするワークでしたが本当についていけませんでした。
当時は能力も経験も足りていないので、周りには迷惑をかけました。
ビジネスという言葉も初めて聞いた勢いでした。
−続いて、地方就活生は就活の際にお金がかかる、という話もよく耳にします。佐山さんが就活にかけたお金はどれくらいでしたか?
佐山:あくまで私の例ですが、総じて50万はかかりました。
東京が主戦場だったので、3月から月に5往復はしていました。平均して交通費が月5万かかるのと、食費は外食などで賄うしかなかったので。
その代わり、宿泊費については友人宅に泊めてもらうなどして抑えることができましたが。
−佐藤さんは仕事柄、地方の学生と関わる機会が多いそうです。今の地方就活生に対して抱く印象はありますか?
佐山:先ほど「きっかけ」という話をしましたが、自分の頃より考えるきっかけはめちゃくちゃ増えているはずです。
当時は3年の2月に始めたら早い方だったのが、今は3年夏のインターンに参加できないという理由で焦り始める人もいますからね。
以前より、地方就活生の間にも「就活が始まっている」という情報が入って来やすくなったと思います。その点「選択肢」は確実に今の方があると思います。
−佐藤さんが考える地方就活生の特徴を教えてください
佐山:率直に思うことは地方就活生は経験も自信もないですよね。だから就活中に少しでも躓いたらすぐに折れちゃいます。
あと情報に触れる経験をしていないので、初めて聞いた話を鵜呑みにしやすい。自分で判断すると言うことに慣れていないと思います。
一方でポジティブな特徴もあると思っています。それは時間に対する考え方です。
地方就活生が東京で就活する場合、時間が限られています。東京までの交通費と宿泊費でかなりのお金がかかるはずで、無駄にはしたくないと思います。
ので、東京に行った時はめちゃくちゃ頑張ります。私も東京に来る際は1日の予定を詰めに詰めて就活していました。
時間あたりの行動の密度が圧倒的に濃いのが地方就活生ですね。そこは強みと言えると思います。
◆ビハインドしている意識を持って…地方就活生にアドバイス
−地方就活生にアドバイスをお願いします。
佐山:まず地方就活生は特に、動き出しは早ければ早い方がいいです。3年の4月には始めた方がいいと思います。
しかし、早く始めたとしても適切なアクションがわからない、と言うことが地方就活生には往々にして起こります。
その際、まずはベンチマークを探してほしい。同じような時期に就活を始めた人が何をしていたのか、とにかく聞いて教えてもらう。
あとは食わず嫌いをしないことです。視野が狭いので、いろんな情報を得るためにイベントに参加するなどとにかく行動してみてほしいです。
その際、地方就活生によく起こりうるのが、参加したいイベントはあるけど移動が面倒ということです。
1つのソリューションとして、就活中の大事な時期は東京に住むという大胆な選択もできると思います。物理的な制約でイベントに参加に対する抵抗をいかに減らせるかはすごく大事です。
参加したいイベントに確実に参加するために地方にいることで生じる機会損失を極力減らしてほしい。
地方就活生の皆さんは、とにかくめちゃくちゃビハインドしていると言う自覚を持って、行動してください。
【企業さまへ】en-courageイベントの年間スケジュール資料があります。フォーム入力の上、ダウンロードしていただき、採用活動にご活用ください。