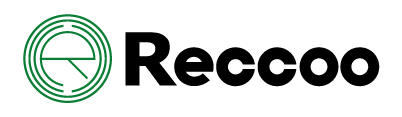目次
・面接の2つの目的
・面接でスクリーニングする方法
・面接でアトラクトする方法
・面接で質問するべきこと/質問してはいけないこと
・本記事のまとめ
面接の2つの目的
説明会やES、適性検査などをはじめとした、採用する人員を定めるために行う採用活動のうち、
直接またはビデオ通話などを介して「面と向き合って接し、話をするもの」、これを「面接」と言います。
では、各採用フェーズごとに目的を確認してみましょう。
「広告や採用メディアへの出稿」は 会社の存在を認知してもらう ために
「説明会」は 会社についての理解を深めてもらう ために
「ESや適性検査」は 採用候補者たちの大体の把握と絞り込み のために
実施しています。
それでは「面接」は何を目的として実施するのでしょうか?
結論からいうと、面接の目的は、
①スクリーニング(ふるい分け) と、②アトラクト(惹きつけ) の2つです。
スクリーニング とは「企業」にとって「ほしい人材要件」を「学生」が満たしているのかを見極め、“ふるい”にかけること。
アトラクト とは「企業」の「魅力的な点」を「学生」にアピールし、入社への動機づけをすること。
つまり、
企業が「学生を選ぶ」ためにするのがスクリーニング
企業が「学生に選んでもらう」ためにするのがアトラクト
ということになります。
先にスクリーニングを実施し、候補者を絞ってからアトラクトを実施するのが一般的です。
また、「面接」に求められる役割として、「クロージング」も含まれることがあります。
クロージングとは、「締めくくり」を意味する語で、採用活動においては、「企業」が「入社への決心」を「学生」に求め、内定承諾 してもらうことです。
一般的には、面接よりもフランクな「面談」や「内定者懇親会」などがその役目を担うことが多いのですが、面接にクロージングの要素を含ませることもあります。
ただし、あくまで面接の基本的な目的はスクリーニングとアトラクトです。
では、この2つの面接の目的を果たすには、どのような動きが必要なのでしょうか?
具体的に「面接でスクリーニング/アトラクトする方法」について確認しましょう。
面接でスクリーニングする方法
「ガクチカ」を面接官がよく聞く理由
「ガクチカ」(=学生時代に力を入れて取り組んだこと)は、面接時において、鉄板とも言える質問です。
では、なぜ面接で「ガクチカ」について質問することが多いのでしょうか?
新卒採用を行う場合、候補者の身につけているスキルだけで判別するのは難しいです。そのため、候補者のポテンシャルを重視して採用することが多いのですが、ポテンシャルというものは具体的に表せる情報ではありません。
そこで必要になってくるのが、候補者の質的な情報(=パーソナリティ) です。
「ガクチカ」を質問することで、学生のパーソナリティについて把握することが可能となり、それを元に、その学生が企業の「欲しい人材要件を満たしているか」の判断(=スクリーニング)が可能となります。
ただし、「ガクチカ」についての情報のみでスクリーニングが可能になるわけではありません。単に「ガクチカ」のみで判別できるのであれば、ESからでも読み取ることが可能です。
あえて「面接」で「ガクチカ」を質問するのは、「詳細の掘り下げ」とその過程での「採用候補者のパーソナリティの明確化」が目的です。
学生が今までに「どのような場面でどのような行動を選択し、どのような結果が得られ、どのように思ったのか」を質問によって掘り下げることで、その情報を元に、企業風土に馴染んでいけそうな人材か判別が可能になります。
また、選考の最終的な局面においては、ここで得られる情報を元に候補者間の 「努力」や「頭の使い方」のレベルを比較する 手助けにもなります。
さらに、深掘りする過程で候補者の「周囲との関わり方」や「コミュニケーション能力」といった、文字だけでは読み取れない部分まで読み取ることが可能となります。
パーソナリティの深掘りが目的なので「ガクチカ」に限らず、候補者の「長所/短所」や「成功/失敗談」などを質問するのも効果的です。ですが、面接の時間は限られているので、「あれもこれも」とならないように気をつけましょう。
どうして面接官は「他に選考を受けている企業」について質問するのか?
「ガクチカ」と同様、「他社の選考状況」も面接における鉄板の質問です。
これを質問する理由は、下記2つです。
①採用競合についての情報を把握するため
②候補者の志望理由や「企業選びの軸」を確認するため
特に、スクリーニングという観点では ②が重要 になります。
例えば、候補者が「ほしい人材要件」を満たしていても……
・「実力主義で積極的なコミットが求められる企業」×「ワークライフバランスを重視したい候補者」
・「研修のサポートが手厚く、教育制度がしっかりしている企業」×「早い段階で裁量を持って業務に関わりたい候補者」
このような企業と候補者の組み合わせでは、互いに望む結果は得られないでしょう。
候補者のパーソナリティが「ほしい人材要件」を満たすことももちろんですが、「企業選びの軸」が企業の価値観に合っていることも重要だと言えます。
「企業選定の軸」の判別する方法としては、
・「志望理由」や「他社の選考状況」などから間接的に聞き出す方法
・「あなたの企業選びの軸はなんですか?」と直接聞き出す方法
の2種類があると言えるでしょう。
面接でスクリーニングする方法のまとめ
1.「ガクチカ」を質問し、候補者の「パーソナリティ」を明らかにする
2.「他社選考状況」を質問し、候補者の「企業選びの軸」を明らかにする
3.「ガクチカ」「他社選考状況」で聞いた内容を元にスクリーニング
面接でアトラクトする方法
「面接」は「選んでいる」と同時に「選ばれている」?
株式会社RECCOOとキャリア教育支援NPO en-courage(エンカレッジ)のアンケート調査によれば、
(2019年6月8日〜15日にかけて20卒483名を対象に実施)「内定承諾先企業の志望度が最も上がった機会」として、最も回答が多かったのは「本選考の面接」(32.2%)でした。
このことから「面接」が持つ「アトラクト」という役割がとても重要なことがわかります。
では候補者の「志望度の上がる面接」は、どのようにデザインしていけばいいのでしょうか?
「志望度の上がる面接」作りのハウツー
「志望度の上がる面接」をデザインするには、
①採用の準備段階で企業の魅力について徹底的に洗い出す
②スクリーニング段階で学生の情報を集め、刺さるアプローチを見極める
この2つのポイントを押さえる必要があります。
効果的に候補者へ企業の魅力を伝えるには、
採用を進めていく人事自身が「企業の魅力」について熟知 している必要があります。
つまり、「採用の準備段階で企業の魅力について徹底的に洗い出す」必要があります。
ここで注意するポイントは「一つの視点から見た魅力」に止まらないこと。人事目線、現場目線、経営者目線から 多角的に「企業の魅力」を洗い出す ことで、学生への魅力訴求がしやすくなります。
次に、「スクリーニング段階で学生の情報を集め、刺さるアプローチを見極める」必要があります。
例えば……
・候補者「ワークライフバランスを重視したい!」ならば……
→企業「フレックスタイムや残業削減のための取り組みをしてるよ!」
・候補者「早い段階で裁量を持って業務に関わりたい!」ならば……
→企業「新卒◯年で事業の責任者として活躍している事例があるよ!」
など、その候補者の求めているであろう環境や待遇などの要素の中から、洗い出した企業の魅力で満たせる要素でアトラクト すると良いでしょう。
また、候補者が求めている要素を企業が今持っていなくても、将来的な可能性としてその要素を満たせそうなら、それもアトラクトに利用できます。
このように、候補者に合った企業の魅力を提示することで、候補者が働くイメージをしやすくなり、自分に関心を持っていることを候補者自身が自覚しやすくなります。
面接でアトラクトする方法のまとめ
1.選考開始前に「企業の魅力」の洗い出しをおこなう
2.スクリーニング時に候補者の「特性」や「価値観」などを確実に聞き出す
3.手にした情報を元に、候補者に刺さる「企業の魅力」でアトラクトする
面接で質問するべきこと/質問してはいけないこと
面接の持つ2つの役割(スクリーニング/アトラクト)について理解したところで、次は実際に面接するにあたって「質問した方がいいこと」と、逆に「質問してはいけないこと」を確認していきましょう。
面接で質問した方がいいことリスト
ー候補者のパーソナリティについての把握を目的とした質問
「学生時代に力を入れたことは何ですか?」
「自分の長所と短所を教えてください」
「成功または失敗談を教えてください」
面接でスクリーニングするためにも、このような質問から候補者のパーソナリティを深掘りし、「ほしい人材要件」を満たしているのか、入社した時に活躍できるビジョンが見えるのか を判断するための材料を得るようにしましょう。
ー候補者の企業選びの軸についての把握を目的とした質問
「あなたの企業選びの軸は何ですか?」
「他にはどのような企業を受けていますか?」
「◯年後、どのような姿になっていたいですか?」
面接でアトラクトをおこなうためには、このような質問で候補者の企業選びの軸、つまり 働くにあたって大切にしたい要素 を明確にし、効果的な魅力訴求のアプローチを見極めましょう。
ー候補者の持つポテンシャルについての把握を目的とした質問
「今までで一番努力したことは何ですか?」
「人生で一番熱中したことは何ですか?」
これらの質問はパーソナリティの把握にも繋がりますが、候補者の持つ ポテンシャル(=将来性) の把握にも繋がります。
新卒採用は中途採用と比べ「今後の成長率」が重要視されます。なので、採用フェーズ後半の絞り込みにおいてはこのような「頑張った経験」のレベル感などから、その候補者のポテンシャルを読み取り、判断材料にしていく必要があります。
面接で質問してはいけないことリスト
採用選考に当たっては、
・応募者の基本的人権を尊重すること
・応募者の適性・能力のみを基準として行うこと
の2点を基本的な考え方として実施することが大切です。
公正な採用選考を行う基本は、
・応募者に広く門戸を開くこと
言いかえれば、雇用条件・採用基準に合った全ての人が応募できる原則を確立すること。
・本人のもつ適性・能力以外のことを採用の条件にしないこと
つまり、応募者のもつ適性・能力が求人職種の職務を遂行できるかどうかを基準として採用選考を行うことです。就職の機会均等とは、誰でも自由に自分の適性・能力に応じて職業を選べることですが、このためには雇用する側が公正な採用選考を行うことが必要です。
(厚生労働省 採用のためのチェックポイント 公正な採用選考の基本より)
このように公正な選考をおこなうためには「求職者の責任ではない事項」や「人権観点で自由が保障されている事項」については聞かないようにしなくてはなりません。
具体的な「候補者に聞いてはいけない内容」としては……
・本籍地について
例:「あなたの本籍地は?」「家族はどこ出身?」
・家族の職業、収入、資産、住居、健康状態など
例:「お父さんはどんな仕事を?」「家庭環境は?」
・候補者の住居への経路や間取り、家賃など
例:「どの辺に住んでいるの?」「一人暮らし?」
・政治や宗教、思想について
例:「どの宗教を信仰していますか?」「支持する政党は?」
・男女雇用機会均等法に抵触する内容
例:「結婚、出産の予定は?」「結婚後も働き続けますか?」
などが挙げられます。
いずれも 「法的」に聞いてはいけない内容 なので、面接担当の社員には注意喚起をしておきましょう。
また、面接官は候補者と「企業の代表者」として向き合うこととなります。その時に取るべきではない行動をとれば、候補者が抱く企業の印象に対してマイナスに働くことがあるので気をつけなくてはなりません。
具体的な「面接官がするべきではないこと」は……
・自社をよく見せようとして、他社の悪口を言う
・候補者に対して常に上から目線、圧迫面接を仕掛ける
・約束した時間を守らずに遅刻する
・ちゃんと面接をせずに雑談ばかりする
・「ここだけのハナシ」と会社の愚痴をもらす
などが挙げられます。
このような内容は候補者の心象を下げることはもちろん、就活口コミサイトなどで拡散されがちな内容でもあります。人事担当はもちろん、人事以外で面接官として採用に携わる社員全員への周知をするようにしましょう。
本記事のまとめ
「面接を最大限に活用するポイント」まとめ
・面接は スクリーニング と アトラクト が目的
・企業が「学生を選ぶ」ためにするのがスクリーニング
・企業が「学生に選んでもらう」ためにするのがアトラクト
→「面接」とは「選んでいる」と同時に「選ばれている」
・選考開始前に「自社の理念、軸」「自社の魅力ポイント」を洗い出す
・面接で聞くこと/聞かないことをハッキリさせる
・「ガクチカ」「努力したこと」「成功/失敗談」はスクリーニングの材料
→アトラクトの魅力訴求ポイントを明らかにするためにも貴重な情報
・候補者の人権を無視するような質問 はしない
・面接官として、企業の印象に悪影響をもたらす行動は慎む
キャリア教育支援NPO en-courage(エンカレッジ)とは
日本全国80以上の大学に支部を持ち、これまでに【10万人以上の学生】の就職活動を支援してきた日本最大級のキャリア教育支援NPO。
「日本の就活を変える」というビジョンに共感いただく企業様も日々増えています。
エンカレッジを活用する学生は20卒約3万人、21卒約5万人と、会員数を次第に伸ばし、22卒会員数は8万人見込みとなっております。
株式会社RECCOOとは
株式会社RECCOO は、エンカレッジと包括的業務提携を結び、上位校を中心とした学生の採用を継続的にサポートしています。
月間100万PVを誇る求人媒体への情報掲載や、イベント開催やご送客を通じた接点創出、さらには学生との面談を通した個別紹介など
幅広いサービスを展開しております。
これまでに300社以上の企業様とのお取引がございます。
ご興味のある企業様は、下記フォームよりお問い合わせください。