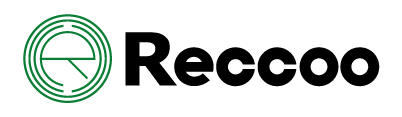就活を終えたエンカレッジ就活生にインタビューする企画。
今回は新卒採用の手法に焦点をあてます。企業が求める人材の多様化により新卒採用の手法が変化しています。面接やグループディスカッションなど、従来の採用手法とは違った選考を経験し、感じたことを人材系ベンチャー内定の山井さんに語ってもらいました。新卒採用手法の最前線を追いました。
【企業様へ】記事末にen-courageイベントの年間スケジュール資料があります。ぜひダウンロードしていただき、採用活動にご活用ください。
◆教育を軸にキャリアをプラン
ー本日はよろしくお願いいたします。早速ですが、片山さんが現在描いているキャリアプランについてお伺いさせてください。
山井さん:内定先は教育系のベンチャー企業です。子供の頃から漠然と教員になりたいという思いを持っていました。
そして大学では教育学部に進学し、幼児期の営業教育というテーマで卒論も書きました。
ー新卒で教員になるという選択肢はなかったのですか?
山井さん:もちろんありました。教職員免許も取得しましたし。そうですね、大学2年生までは自分は将来教員になるんだろうなと考えていました。
しかし、自分の将来像を考え直すきっかけもありまして、大学3年の夏からは就活を初めていましたね。
ー具体的にキャリアを考えるきっかけになったことを教えてもらえますか
山井さん:はい。私は国際ボランティアの団体に所属していて、定期的に発展途上国へ行き、子供たちに英語や、算数など教える活動を行なっていました。
その時に世界が広がったといいますか教育に関わるというは教壇に立って教えるだけではないんだなと気づいたんです。
キャリア支援だったり、国際ボランティアの文脈でも、自分の「教育に関わりたい」という欲求が満たされるなと思いました。
ちょうどボランティアに参加する直前に教育実習に参加していて、ある種決まったのレールの上を歩いているような人生でした。
しかし、いざ違う世界に飛び込んでみるとまだ自分は狭い世界しか見ていないと気づきました。そうなった時にその狭い視野でキャリアを決めてしまってもいいのだろうかという思いを抱きました。
そこで、周りも続々と就活を始める時期でもあったので、まずは広く浅くでもいいので社会を見てみようと思い、就活をはじめました。
◆教育を軸にキャリアをプラン
ーありがとうございます。続いて具体的な就活の進め方についてお聞きしたいと思います。まず情報収集はどのようにやられていましたか?
山井さん:よくあるナビ媒体には一通り登録はしていました。が、ただ登録していただけで使い倒していたというわけではないです。
主な情報収集としては人伝てが多かったですね。月並みな話になってしまいますが、ネットでなんでも検索できる時代だからこそ、しっかりと対面して、感じ取れる生の情報を大切にしようと思っていました。
これは就活を進めるにあたって、私のモットーでしたね。
なので先輩や、友達の時間を抑えてもらって、ひたすら自分の就活の軸を語っては感想をもらっていました。
ーなるほど受けた業界/企業はやはり教育系が多かったのでしょうか?
山井さん:最初は教育に少しでもかかわる企業や業界は本当になんでも見ていました。例えば、人材業界から外資系のコンサル、チームビルディングなど研修プログラムにも興味を持ったのでそれを斡旋している企業といった感じです。
コンサルの面接で印象的なことがありました。志望動機を聞かれるわけですが、私は教育という軸に絡めて志望動機を述べていましが、ある面接官には「君の教育に対する熱量はものすごく伝わってきた。でもなんでコンサルなのかは全くわからなかった」とか言われていましたね。
新卒採用の手法としても、リクルーター面談のように、一般的な面接よりも時間を使って私という人間を深掘りしてくれるような選考をしてくれる企業はやはり印象に残っています。
◆手法①【逆求人】
ーありがとうございます。それでは本題の、変わった新卒採用の手法についてお聞きしたいと思います。順番に教えていただいてもよろしいでしょうか?
山井さん:まずは逆求人(スカウティング)型の採用手法です。某ナビ媒体に登録し、自己PRや「学生時代に力を入れこと」を記入すると、企業の人事が連絡をくれます。
単なる説明会のや選考の案内ではなく、直接会う日程を先に立ててくれるので、とにかく人に会う就活をモットーにしていた自分にとっては、都合のいい採用手法だと思っていました。
ー実際その新卒採用の手法を経て選考はどのように進んで行くのですか?
山井さん:はい、その面談を行った人はリクルーターのような形でその後の選考もサポートしてくれました。結局グループディスカッションの選考を通過し最終面接まで進みましたた。
最終面接の前も相談に乗ってくれましたね。
やはり、逆求人ということで相手に求められているので、丁重に扱ってくれるといいますか。普通の面接だと「では、さようなら」という感じで寂しいじゃないですか。
完全に好みの問題ですが、私個人的にはとしては好きな採用手法でした。
◆手法② 【焼肉採用】
ー「焼肉採用」…。そんな新卒採用の手法があるんですね。いったいどのような選考手法だっったのでしょうか。
山井さん:参加したインターンのグループワークで優勝して、そのご褒美の食事会として設定されました。
そもそも平日の夜 に行われて、ということは社員の方が忙しい合間を縫って開催していたので選考に関係ないわけがないな、と思ってはいましたね。笑
参加者は人事の方3名と学生はグループワークで同じグループだった6名です。
普通に焼肉を食べながらの楽しい会でしたが、当然人事の方が話を回してくれて、子供の頃から今に至るまで、どんな人生を歩んできたのかを関係のない話を挟みつつ、聞いている印象はありましたね。
ー「焼肉採用」後、その後の採用手法はいかがでしたか?
山井さん:結局その後、2回の面接を経て内定をもらいました。「焼肉採用」を経験したメンバーのうち半分が面接に進んでいました。
インターン時の成績なのか、焼肉での印象がどう作用したのかはわからないですが…。
-変わった新卒採用手法を経験したわけですが、どのような心境で臨みましたか?
山井さん:最初は焼肉を楽しもうと思っていましたが、先ほど述べたように途中から本当の面接のような質問が飛んできたので、そこは流石に切り替えましたね。
それでも面接は経験していたので焦ることなく進められたと思います。が、時間が長いこともあって、結構深掘りました。就活の軸はしっかり整理していた方だとは思いますが、これを機にもう一度自己分析をしようと思いました。
-この新卒採用手法を選択した企業の狙いはなんだと思いますか?
山井さん:焼肉を食べているときに人事の方が既存の採用手法への課題感を仰っていたのは印象に残っています。
例えば一般的な面接。時間も限られている中でしかも、それに対して「これでいいですよね?」みたいに就活生としての最適解を答えてくるんだそうです。
人事の方は、学生がどんな人間か知りたい、素を見たいということを仰っていました。
ご飯を食べてリラックスしている状態で素を引き出す。この手法の狙いはまさにそれだったのかなと思います。
―他の新卒採用では経験できないはずです。心がけたことはなんですか?
山井さん:人事の方も仰っていたように、ありのままで臨むことが大事だと思っていました。選考だからといって変に力まず、普段やらないことはしないとか。
一方で私はできていなかったのですが、人事の方の飲み物がなくなった時に注文をするなど、自然と気を使えていた人がいて、普通に感心していましたね。
もちろんそれが評価されたのかどうかはわかりませんが。
◆手法③ 【合宿選考】
―最後に最も驚いた採用手法を教えてください。
山井さん:合宿選考ですね。1泊2日間の日程で行れました。IT系の企業の選考だったのですが、ITとかけ離れたというか、とても刺激的な合宿でしたね。
―合宿選考。最近大手総合商社でもこの採用手法を取り入れたと聞いています。どのような内容だったでしょうか?
山井さん:年によって内容は違うようですが、私が参加したのは山でキャンプをするというような内容でした。1グループ6人のチームを組みまして、もちろんただキャンプするのではなく、参加中に色々課題が出されます。
火を起こしたり、山の中から食料を取って食べるだったりとか。テレビのバラエティ番組のような企画でしたね。
チームは当然初めましての人同士で組まれるので最初は探り探りですが、途中から打ち解け、そして当然仲間割れもします。
おそらく仲間割れのような悪いチーム状態になることもこの採用手法の狙いの一つで、メンバーのベクトルが違う方向を向いた時にそれをどのように正していくのか。そしてそれをどのメンバーが率先してやるのか、という点を企業側は意識していたのではないかと。
個人的には企業が用意してくれた、チームビルディングのコンテンツが一番印象的でした。コンテンツとして提要している別の企業の方が講師としてついてくれたのですが、新しい「教育の手法」を見たような気がしてとても新鮮でした。
―こちらの新卒採用の手法、企業の狙いはなんだと思いますか?
山井さん:繰り返しになってしまいますが、やはり素が見たいということだと思います。長くても30分という短い時間の中での評価として、人生の選択を迫るということは企業の方もリスクを感じているのではないでしょうか?
短時間の面接ではそれこそ「演じる」ことが可能ですが、時間をかけ、さらに普段の生活とはかけ離れた日常を送るわけですから、その人の本質が見えてくると思います。
学生としても、これは私個人の意見ですが、数十分の面接で人生の大きな選択を迫られてしまう、一般的な面接という手法よりも理にかなっている手法なのかなと思います。
―最後に変わった採用手法をいくつも経験されわけですが、就活生はどのように対策していけばいいのでしょうか?
山井さん:まず質問の前提を覆すようですが、採用手法ごとに対策をしないのが良いのかなと。
一般的な面接やGDなどは対策がや練習が成果になる人もいると思います。しかし私が経験したような特殊な採用手法において、対策は時間の無駄です。
というのも人事の方は、全く武装していないありのままの就活生を評価したいと思っているはずです。
対策ではなくいかに自分表現するか。企業は素の学生を見たいのですから。
就活生のみなさんは自己分析もしているでしょうし、自分がどんな人間かはいくらか把握していると思います。
それをそのまま表現することだけを心がければ良いのかなと思います。
―山井さん、インタビューありがとうございました!
【企業さまへ】en-courageイベントの年間スケジュール資料があります。フォーム入力の上、ダウンロードしていただき、採用活動にご活用ください。