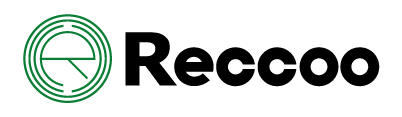●目次
1.新卒採用におけるコストとは?何に費用がかかるのか
2.採用費用はどのくらい?サービス別に解説
3.一般的な新卒の求人媒体の費用は抑えやすい?
4.どんなサービスを選ぶべき?選ぶポイント
1.新卒採用におけるコストとは?何に費用がかかるのか
まずはじめに新卒採用における、基本的なフローを確認します。
・採用目標の決定、計画の策定
・企業認知/興味づけ(選考参加学生の獲得)
・選考/スクリーニング
・内定後フォロー/内定後研修など
・採用目標の決定、計画の策定
この段階では、採用コンサルティングを行っている企業などに対して、費用を支払っている場合などがあるようです。卒業年度ごとに契約を行い、1年間のフィーで、採用活動全体に併走してくれます。
・企業認知/興味づけ(選考参加学生の獲得)
具体的に費用がかかる項目は、以下のようなものです。
・就活生が見ている媒体への広告掲載
・大手人材企業が提供するナビ媒体への求人掲載
・企業説明動画や、紙媒体のチラシ、パンフレット
・説明会の会場費用や出張費など(個社で実施する場合)
・イベントへの参加費用
それほど一般的ではありませんが、新卒採用で人材エージェントを活用している場合に、成果報酬以外で、着手金という形での前金が発生する場合もあるようです。
・選考/スクリーニング
選考の早い段階で学生に受けてもらうWebテストや、選考を実施する際の交通費などがかかります。またグループ面接などを外注している場合には、その分のコストが発生します。
大手企業においては、リクルーター制度を活用しているところもあるため、リクルーターへの研修に対しても費用が発生することになるでしょう。
日本の大手企業では、数百名のリクルーターの研修や、交通費などを合わせると、それだけで数千万円規模になることもあるようです。
・内定後フォロー/内定後研修など
多くの企業では6月に本選考が解禁され、およそ1ヶ月の間に内定出し、内定承諾のピークを向かえることになります。
入社に内定者研修を行う場合には、その分のコストが発生します。東京などの本社で、まとめて選考を行う場合には、交通費の負担を企業側がすることが一般的なようです。
2.新卒採用にかかる費用はどのくらい?サービス別に解説
一概に費用といっても、サービスごとにかかる金額は大きく異なります。
今回は、新卒採用における、最初のステップである母集団形成に関わるサービスをまとめていきます。解説するものは以下の通りです。
・ナビ系求人媒体
・合同説明会(大学内/大学外)
・新卒人材紹介エージェント
・ダイレクトリクルーティング
・ナビ系求人媒体
ナビ系の媒体における利用料は、主に初期費用と月額の利用料金です。
大手人材系の企業が提供するナビ媒体の場合には、掲載期間が1ヶ月単位ではなく新卒採用のスケジュールと連動していることがあるため、1ヶ月単位で契約できる場合と比較して、高額になるケースが多くなります。ただし、大手の媒体は利用する就活生の数が数十万人になるので多くの就活生との接点を持てる可能性があります。
ナビ媒体を利用している企業は、約3-4万社ほどあるようで、新卒採用をしている企業の多くが利用しているサービスではないでしょうか。
・合同説明会(大学内/大学外)
インターンや、本選考前の合同説明会は、参加するイベントごとに費用を支払うのが一般的です。
合同説明会においては、企業の特別講演や、特別ブースを設置している場合があり、オプションとして追加のコストが発生します。金額はイベントの規模にもよりますが、およそ20~60万程度のことが多いようです。
合同説明会は大学内で実施をしているケースもあり、特定の大学に在籍する就活生に対しての企業PRが可能です。学生から人気がある特定の企業に対しては、イベント出展にかかる費用を安くしているケースもあり、中には、無料のケースも存在しているようです。
・新卒人材紹介エージェント
新卒人材紹介エージェントを活用する場合には、契約内容によって大きく費用が変わります。
成果報酬は主な形態の一つですが、どの時点を成果とするかにもパターンがあり、「企業への内定承諾」なのか、「企業へ入社」なのかによっても条件が変わってきます。
ただし、中途の人材紹介で成果と設定されることが多い、「入社から3ヶ月間継続して勤務」といった契約はほとんどないようで、多くの場合には、企業への内定承諾を成果とすることが多いようです。
・ダイレクトリクルーティング
ダイレクトリクルーティングの費用体系は、求人媒体系のサービスと、新卒人材紹介エージェントを合わせたものがイメージしやすいかと思います。
例えば、月額費用として、10万円前後を支払うことで学生へのオファー活動が可能になり、学生が内定を獲得した時点で、数十万の成果報酬を支払うパターンなどです。
新卒人材紹介のエージェントよりは、成果報酬の金額は低く設定されているので、コストを抑えたい場合には、使っていることが多いようです。ただし、コストが低い分、時間をかけて丁寧に利用しなければ、オファーを出しても学生が承諾しない場合も...。
最近では、学生からの認知度も高まり、十万人以上の就活生が利用しているサービスも出てきています。
以上が、各サービスの基本的な費用になります。
3.新卒の求人媒体の費用は抑えやすい?
新卒採用でかかるコストにおいて、大きな割合を占めている母集団形成に関わるコスト。
どのようなサービスを活用するかによって、費用は大きく異なりますが、基本的に成果報酬以外の携帯であれば、工夫次第で採用コストを低く抑えられる可能性が大きいです。
例えば、前述の「ナビ系求人媒体」の場合には、費用の合計は「契約の初期費用」と「月額利用料」が基本です。媒体から得られた成果の量は費用に影響しないため、成果次第ではコストを大きく削減することができます。
ただし、媒体掲載は、学生にある程度名が知れていることが前提となるので、知名度があまり高くない企業の場合には、媒体掲載だけで学生からの応募を見込むのは難しいでしょう。
そのため、媒体には企業の知名度や認知度を高めるために、オプションとして就活生へのメルマガ配信や、掲載順位を上げると言ったサービスがあります。予算と相談しながら、オプションを上手く組み合わせることも検討するといいでしょう。
また、媒体のサービスを利用する場合には、就活生の選考状況を管理するツールとのセット利用が一般的です。その利用費としてさらに追加コストがかかるケースもあるようですので、注意が必要です。
4.どんなサービスを選ぶべき?選ぶポイント
ここまで、新卒採用におけるコストについて、選考フロー別、サービス別に解説してきました。
では、実際に予算と相談しながら、新卒採用の手段を決める際には、何を意識するべきなのでしょうか。
コスト面以外で、大きくは以下の2つです。
・採用したい学生がどの程度、利用しているのか
・サービスの利用にかかる時間
・採用したい学生がどの程度、利用しているのか
どれだけ金額的に安いサービスであっても、採用計画時に想定した採用ターゲットとなる学生が利用していない場合には、あまり効果がありません。
以前、弊社で就活生にアンケートを行ったところ、就活生は複数のサービスを組み合わせて利用しているというアンケート結果になりました。
特に最近では、ナビ媒体だけで就活をしている学生は減ってきているようです。そのため、採用したいと思う学生が使っているサービスを見極めて採用手法に盛り込んでいく必要があります。
・サービスの利用にかかる時間
費用面と同じくらい問題となるのは、採用担当者にかかる時間的な負担ではないでしょうか。特に最近では、学生の就職活動の開始時期が早期化しているというアンケート結果も出ています。
就職活動が早期化している近年においては、前年度の選考と今年度の採用活動の期間が重複が大きくなる傾向にあります。少しでも採用担当者の負荷を減らしたい場合には、利用から採用までにどの程度の時間や手間がかかるのかを、確認しておく必要があるでしょう。
例えば、採用担当者がオファーを出すことで採用活動が進むダイレクトリクルーティングのようなサービスでは、担当者の負担が大きくなります。どうしても利用したい場合には、新卒紹介エージェントや、採用を代行する企業も効果的に活用するといいでしょう。
採用手法だけではなく、オプションや外部委託もうまく組み合わせることで、費用に見合った採用活動を行えると良いですね。
株式会社RECCOO
株式会社RECCOOでは、全国で200回以上のイベントを開催しています。また、イベントだけではなく優秀な個別学生のご紹介など、貴社の採用計画に合わせたサポートをしています。
日系大手企業様から、創業間もないスタートアップ企業まで年間300社以上の企業様に対して採用支援を行なっております。弊社のサービスマップは以下からダウンロード出来ます。
エンカレッジへのお問い合わせはこちら
イベント出展や新卒紹介など、エンカレッジへのお問い合わせはこちら