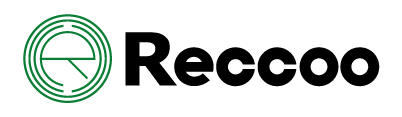新卒採用のスケジュールが今、転機を迎えています。
新卒一括採用に陰りが見え始める中、2021年入社(以下21卒)の学生の採用スケジュールは、どう変わるのでしょうか。優秀な学生を採用するために不可欠な採用スケジュールの策定について、基本的なポイントをお伝えします。
目次
1 新卒採用スケジュールの重要性
2 新卒採用の基本的な流れ
3 経団連の「就活ルール」とは
4 形骸化する「就活ルール」の実態は?
5 21卒の採用スケジュール策定のポイント
新卒採用スケジュールの重要性
新卒採用のスケジュールの策定は、1年間の動きを決定する大変な業務です。しかし、しっかりと情報収集をして計画を立てることができれば、求めている学生と適切なタイミングで接触をし、採用に繋げることができます。
一方で、スケジュールの重要性を理解しつつも「何を基準に決めていけばいいのかわからない」という採用担当者の方も多いかもしれません。
では、そもそも企業にとって採用スケジュールの策定は、なぜ必要なのでしょうか。
考えられる背景は、大きく以下の2点です。
------------------------------------
・学生接触、選考開始、内定出し等のタイミングを誤ると、本来であれば自社に入社してくれたはずの学生さえも、他の企業に流れてしまう。
・いざ採用活動を開始してからのスケジュール変更は難しく、無理な選考時期の移動や追加募集は、採用担当者にとっても負担になる。
------------------------------------
また、採用スケジュールは、毎年使い回せる訳ではありません。なぜなら、採用活動の適切なタイミングは、自社の都合だけではなく、多くの外部要因に依存するためです。
例えば、採用スケジュールの指標である「就活ルール」(後述)の方針転換や、就活生の動向の変化が出てきた場合、また、ライバル企業が採用を早めた場合は、企業はそれに応じてスケジュールを適切に見直すことが求められます。
以上からわかる通り、採用スケジュールの策定は、企業の採用活動全体の成否を分ける重要な要素であると言えるでしょう。
新卒採用の基本的な流れ
具体的な注意点の前に、まずは新卒採用の基本的な流れをご紹介します。
企業ごとに採用人数や業界、採用活動の方針は異なるため、全てがこの通りではありませんが、現在、日本において新卒採用形態の中心である「新卒一括採用」を実施している企業では、以下の流れが基本となります。
------------------------------------
①戦略策定
-採用人予定人数決定
-採用予算決定
-採用要件やコンセプトの決定
-採用スケジュールの策定
②採用準備
-イベントコンテンツ決定
-選考内容決定
-選抜基準決定
-インターンシップの開催
③募集 ※「20卒」経団連の解禁日:3月1日
-説明会(合同企業説明会/個別企業説明会)実施
-エントリー受付
④選考 ※「20卒」経団連の解禁日:6月1日
-書類選考
-適性検査
-面接
-随時追加募集
⑤内定 ※「20卒」経団連の解禁日:10月1日
-内定出し
-内定者フォロー/内定辞退防止施策
-入社受け入れ準備
⑥入社
------------------------------------
今回、インターンシップは、採用の前段階という意味で②に分類しています。
しかし実際には、サマーインターンやウィンターインターン、長期インターンなど、多くの企業が通年で学生との接触機会を設けています。
学生側のインターンシップ参加率も年々高まっており、採用スケジュールを立てる上でも、無視できない要素となっています。
スケジュールを考える上では、選考開始の時期に縛られるだけでなく、ライバル企業が「どのタイミングでどんな目的のインターシップを実施しているか」も参考になるでしょう。
経団連の「就活ルール」とは
新卒採用のスケジュールは、企業が0から自由に決定できる訳ではありません。
採用担当者の多くが、「就活ルール」という言葉を耳にしたことがあると思います。スケジュールを策定する際は、まず初めにこのルールを抑えておく必要があります。
「就活ルール」とは、日本経済団体連合(経団連)が発表している、新卒採用に関する指針のことです。経団連に加盟している大手企業などは、この指針を元に採用を進めてきました。
指針で具体的に示されている内容は、採用における「広報活動」「選考活動」の定義づけや、それぞれの解禁時期、インターンシップの位置付けなどです。
例えば、指針の最新版(2017年改定)では、以下のように定義されています。
------------------------------------
●広報活動
広報活動とは、採用を目的として、業界情報、企業情報などを学生に対して広く発信していく活動を指す。
開始時期:卒業・修了年度に入る直前の3月1日以降
●選考活動
選考活動とは、一定の基準に照らして学生を選抜することを目的とした活動を指す。
開始時期:卒業・修了年度の6月1日以降
●採用内定日
正式な内定日は、卒業・修了年度の10月1日以降とする。
------------------------------------
※詳細な情報は、下記リンクからご覧いただけます。(2019年1月現在の最新版)
経産省「採用選考に関わる指針」
経産省「採用選考に関わる指針」の手引き
形骸化する「就活ルール」の実態は?
企業の採用活動を制限する就活ルールですが、実際には、一部大手を除くの多く企業が、解禁日以前に何かしらの活動をしているようです。形骸化している背景には、就活ルールがあくまで自主的なルールであり、違反しても企業に対して特別な罰則は与えられないという事情があります。
また、経団連に加盟していない企業は、初めから指針を遵守する必要がないため、外資企業やベンチャー企業などを中心に、早期からの採用活動を行なっています。
学生側も、早期に動きだす層は、就職活動に対して意欲的あったり、自分のキャリアと向き合う時間が十分取れたりすることが推察できます。企業は少しでも早く優秀な学生と接触しようと、益々採用活動を早めることになります。
以上のように、企業に対して効力が弱まっていると言える就活ルールですが、2018年頃から大きな転機を迎えています。
転機とは、2018年9月に経団連が発表した採用日程の廃止です。具体的には、現在の大学2年/修士1年にあたる2021年卒業の学生(以下、21卒)以降の採用スケジュールについて、就活ルールを撤廃するとしています。
現在は、政府を中心として新たなルール作りが進められていますが、21卒の採用については、学生の混乱防止などの観点から、これまで同様の日程を維持する流れになっています。
企業にとってこの方針転換は、今後無視できない動きと言えます。
21卒の採用スケジュール策定のポイント
20卒と同様のスケジュールで進むことになった21卒の新卒採用ですが、企業のスケジュール策定は昨年と同じでいいのでしょうか。
実際には、22卒以降の大幅な方針変更の可能性を見据え、各企業、以下のような変化が起こることが予想されます。
------------------------------------
・19卒から20卒にかけて進んだ学生の動き出しの「早期化」が加速する
・それに合わせてインターンシップなど、早期からの接触を試みる企業が増加する
・通年採用に近い採用を導入する企業が増加する
------------------------------------
また、企業によっては、スケジュール以外の観点で
・学歴や卒業年度に縛られず、学生個人のスキルを重視する企業が増加する
といった選考基準の見直しも考えられます。
21卒の採用スケジュールを策定する際には、以下のことを意識してみるといいかもしれません。
------------------------------------
・従来の新卒採用スケジュールに縛られすぎず、ライバル企業の動向に付いて行く
・ターゲット学生の就活動向や大学の行事予定までチェックし、タイミングを狙った活動を行う
------------------------------------
2点目の学生動向については、学生が所属する大学や居住地域、文理などでも違いが生じます。企業が設定するターゲットごとにタイミングを合わせた採用活動が求められます。
以上が、企業が策定する新卒採用のスケジュール策定に関する概要です。
貴社の属する業界や採用ターゲットに合わせたスケジュール策定に、ぜひお役立てください。
「20卒学生の就活早期化」レポート
19卒と20卒を対象、1000名規模のアンケート調査を実施!
1年間でどのくらい早期化が進んだのでしょうか。
詳しいレポートは、下記リンクからダウンロード可能です。
「20卒就活の早期化レポート」はこちら
ぜひ、採用活動にお役立てください。
エンカレッジへのお問い合わせはこちら
イベント出展や新卒紹介など、エンカレッジへのお問い合わせはこちら